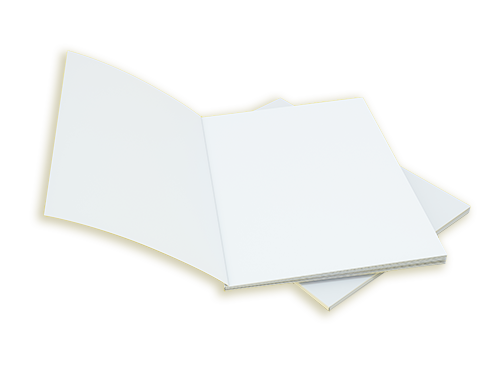アセトアルデヒドの基本特性
アセトアルデヒドは無色透明の液体で、エタナール、エチルアルデヒド、酢酸アルデヒドとも呼ばれます。沸点が21℃と低いため、容易に揮発して気体へと変化します。また、引火点は-38℃で極めて引火しやすい性質を持っており、涼しい場所に保管することが重要です。水、エタノール、ジエチルエーテルに非常に溶けやすい特徴を有しています。
- 硫化水素の主な特徴
- 分子式CH3CHO
- 分子量44.05
- 沸点21 ℃
- 融点-123 ℃
- 引火点-38 ℃
アセトアルデヒドの発生要因
アセトアルデヒドは自然界に元から存在している物質です。それだけでなく、人間のさまざまな活動によっても発生します。
植物、食品からの発生
アセトアルデヒドは、果実や野菜、パンなどの食品中で微量に発生します。また、ビール、ワイン、蒸留酒などのアルコール飲料では、醸造の過程でアセトアルデヒドが生成されます。
さらに、トドマツやカラマツをはじめとするさまざまな樹木にも含まれていて、大気中へと放散されています。つまり、アセトアルデヒドは自然の中でも発生しており、微量ながら常に存在している物質と言えるでしょう。
飲酒、喫煙による発生
アセトアルデヒドは人工的な活動からも発生しています。例えば、人が飲酒によりアルコールを摂取すると、アルコールは体内で代謝されてアセトアルデヒドが生成されます。また、タバコの煙にもアセトアルデヒドは含まれています。タバコの煙の場合は主流煙より副流煙にアセトアルデヒドが多く含まれているとされています。
産業による発生
アセトアルデヒドはガソリンの燃焼によっても生成します。その他に木材の燃焼の際などに発生しており、化学工業などの工場が稼働する過程でも多くのアセトアルデヒドが生成されています。さらに、住居を建設する際に使用する接着剤や塗料などからもアセトアルデヒドは発生します。
アセトアルデヒドによる影響
環境への影響
環境中には常に一定量のアセトアルデヒドが存在しています。これらは、樹木から自然発生するものと、車の排気ガスや工場などから排出されるものがあります。なお、大気中のアセトアルデヒドは、冬よりも夏に多いことが分かっています。これは、光化学反応によって二次的に生成されたアセトアルデヒドが原因と考えられています。
人体への影響
高濃度のアセトアルデヒドは人体に有毒で、強い刺激臭があり、眼や鼻、喉、皮膚などに刺激を与えます。眠気やめまいが出るほか、長期間にわたって何度も高濃度の環境で活動した場合には、呼吸器障害を起こす危険性が有ります。また、発がん性もあるとされます。
飲酒時にアルコール代謝によって生成される量のアセトアルデヒドも、吐き気や動悸、顔が赤くなるといった作用を起こし二日酔いの原因になると考えられています。
ただし、低濃度であればそれらの心配はありません。アセトアルデヒドは自然界に存在し、食品の中にも含まれている物質なので、微量であれば代謝することができます。
アセトアルデヒドの商業利用
アセトアルデヒドは酢酸の製造に利用されており、防腐剤や防カビ剤、防虫剤として使用されています。
また極微量では果実のような香りがすることから、欧米では以前から香料として食品に使われてきました。近年は日本でも食品添加物の香料としての使用が認められ、フルーツジュースやソフトドリンク、乳製品などいろいろな食品に添加されています。
アセトアルデヒドの産業上の取り扱い注意事項
アセトアルデヒドは揮発しやすく引火しやすい物質のため、換気の良い場所に保管し、常に密閉しておくことが大切です。高温下での放置は避け、火花を発生させないような状態で使用する必要が有ります。
また、体内に取り込むと危険なため、作業後には手を洗い、アセトアルデヒドを扱う現場での飲食や喫煙は避けるべきです。作業時には保護用の手袋やメガネなどを使用し、作業で汚染されてしまった衣服は作業場から外へ出さないよう注意が必要です。
アセトアルデヒドの測定方法
アセトアルデヒドを管理するには、アセトアルデヒドの量を定期的に測定することが重要です。
アセトアルデヒドの測定方法には、GC-MSによる微量濃度分析のほかに、ガス検知管やガスセンサーを使った簡易的な検出手段を使った測定方法も有り、目的や使用環境に応じて適切な手法が使われています。
「SGC」関連製品
読まれていますガスセンサーナビ「SGC」関連記事
- 光触媒による水素製造の基礎研究で微量水素の測定を可能にするセンサーガスクロマトグラフSGC
- 呼気アセトンの測定事例―センサーガスクロマトグラフSGC
- 作業環境測定に適した臭気測定器―センサーガスクロマトグラフSGCの紹介
- ステンレス鋼の特徴と種類―系統ごとの性質や水素脆性との関係も解説
- SGC(センサーガスクロマトグラフ)は従来のガスクロと何が違う?―その特徴と活用シーン
- 【水素脆性の評価】水素濃度を測定する方法と試験に使用する装置
- 野菜や果物におけるエチレンの応用と測定装置を紹介
- 破断面から読み取る破壊の原因―破面解析でわかる金属の破壊形態
- 水素脆化と水素侵食―水素が引き起こす2つの損傷現象
- 水素脆性の試験方法―遅れ破壊の可能性を把握するために
- めっきの目的と種類‐表面処理から電子部品としての機能まで
- 脆性破壊の原因と対策―鉄鋼が脆化してしまうメカニズムとは?
- 水素脆性とは?原因から対策までを徹底解説