ブログ
発泡スチロールの代替品は?脱プラの背景・代替品のメリットとは
2025/05/23
- サステナブルパッケージ
- パルプ
- プラスチックごみ問題
- 環境対応
- 脱プラ
- 規制
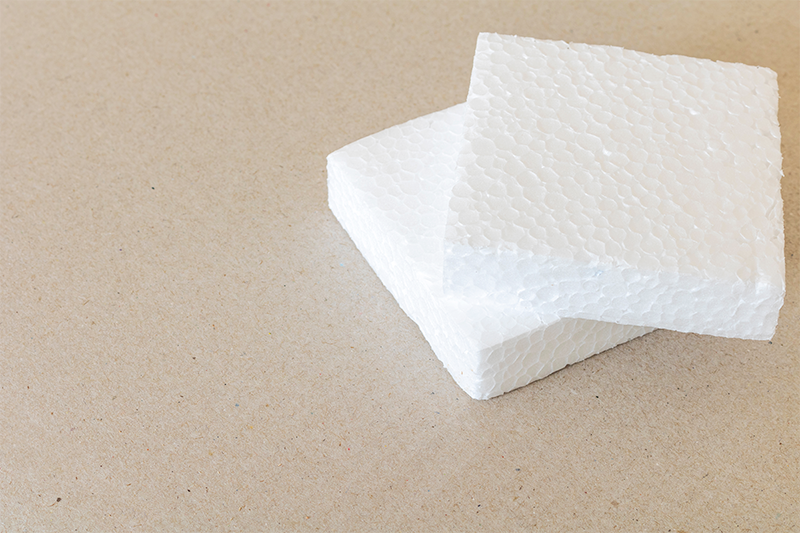
発泡スチロールとは、石油から作られたポリスチレン(PS)を小さい粒状の原料ビーズにし、それを膨らませたものです。日本においては、原料ビーズを使う発泡スチロール(EPS)の製造方法をビーズ法と呼びます。発泡スチロールは軽量かつ断熱性能も高いことから、食品容器や製品の緩衝材、建築資材など、多様な業界で幅広い用途に活用されています。
しかし、発泡スチロールは石油由来のプラスチック製品です。不適切に処理された場合、地球環境に悪影響を及ぼす可能性があるため、近年は「脱発泡スチロール」「発泡スチロール廃止」の動きが世界的に進んでいます。
この記事では、脱発泡スチロールの背景や発泡スチロールの代替品、代替品を活用するメリットを詳しく紹介します。環境規制に対応できる包装資材を探している方は、ぜひ参考にしてください。
世界では脱発泡スチロールの流れになっている?
近年では、発泡スチロールによる環境負荷が問題視されており、欧米を中心に世界各国で発泡スチロールの使用を制限・禁止する動きが見られます。なお、海外における「EPS」は必ずしもビーズ法の発泡スチロールを指すわけではありません。日本では「EPS=主にビーズ法の発泡スチロール原料とその成形品(Expandable Polystyrene/Expanded Polystyrene)」であるのに対し、海外では「EPS=主に発泡スチロール成形体全般(Expanded Polystyrene)」を指します。
そのうえで、以下では世界各国における脱発泡スチロールの取り組みの中で、ビーズ法EPS成形品にも適用される一例を紹介します。
- <EU(欧州連合)>
- 特定プラスチックによる環境影響低減指令(SUPD)で、特定の発泡スチロール製食器、飲料カップを禁止
- 包装および包装廃棄物に関する欧州議会および理事会規則(PPWR)で、容器包装全般を規制
- <アメリカ>
- 2035年までに連邦政府の全業務で使い捨てプラスチック素材の使用を廃止
- ロサンゼルス市条例で、食品に使用される発泡スチロール製の保冷箱類を規制
- <オーストラリア>
- 緩衝包材を含む一部の発泡スチロール製品を規制
- <イギリス>
- イギリス国内で製造または輸入される「再生プラスチック割合が30%を満たないプラスチック包材」に1tあたり200ポンドを課税
- <中国>
- 小売や通販、テイクアウトなどの幅広い分野において、使い捨て発泡スチロール製の飲料容器が規制対象となる可能性
脱プラスチックや発泡スチロール廃止への取り組みは日本でも徐々に広がっています。たとえば、日清食品株式会社は食品容器に発泡スチロールを使うのではなく、「バイオマスECOカップ」を採用しています。2024年4月には、ソニーグループが大型テレビの梱包に使用する発泡スチロール緩衝材の廃止を発表しました。
発泡スチロールが与える環境への影響

発泡スチロールは軽量で扱いやすく、断熱性・緩衝性・耐水性に優れることが利点です。加えて製造コストが低く大量生産が可能であることから、食品用保冷箱や家電製品・精密機器の緩衝材、建材・断熱材など、幅広い用途で活用されています。
しかし、その一方で環境面での問題も指摘されており、その代表例が「海洋ごみとしての懸念」です。環境省によると、海洋プラスチックごみのうち約8割が発泡スチロールであると報告されています。これは、発泡スチロールが軽量で水に浮きやすく、風や波の影響で流されやすい性質を持つためです。
出典:国立大学法人 東京海洋大学「令和 5 年度 沖合海域における漂流・海底ごみの分布調査検討業務報告書」
使用済みの発泡スチロールの大部分はリサイクルされていますが、川などに不法投棄されるケースもあります。適切に廃棄されなかった発泡スチロールは川や排水溝を経由して海に流れ込み、そのまま漂流します。海洋プラスチックごみは時間の経過とともに劣化し、細かく砕けてマイクロプラスチック化します。マイクロプラスチックを海洋生物が誤って摂取すると、生態系にも大きな影響を及ぼします。
発泡スチロールの代替品
脱プラスチックに向けて、世界中では発泡スチロールの代替品としてさまざまな素材が活用されています。ここからは、発泡スチロールの代替品の特徴・メリット・用途を紹介します。
紙・ダンボール

発泡スチロールの代替品として広く利用されているのが、紙・ダンボールです。これらの素材はさまざまな形状があり、包装する内容物や用途によって使い分けることが可能です。
たとえば、紙を何重にも重ねて筒や管のようにした「紙管」は、商品保護用の緩衝材や段積みの補強支柱材として利用されています。紙で作られているので、使用後はリサイクルが可能です。発泡スチロールはもちろん、木材で作られた緩衝材の代替としても活用できます。
また、ダンボール製の緩衝材は、商品の形状に合わせて設計することで、発泡スチロールのように内容物をしっかりと保護する役割を果たします。ダンボールは強度が高い上に発泡スチロールに比べて薄いため、保管や廃棄処理が容易になる点もメリットです。
梱包用のダンボールに商品を詰めるときにできる隙間は、クラフト紙で埋める方法もあります。クラフト紙を丸めるだけで隙間を埋められるので、梱包の手間を省けます。発泡スチロールと比べて安価なのもクラフト紙の特徴です。
生分解性プラスチックや植物・動物由来素材の発泡体

生分解性プラスチックや植物・動物由来素材の発泡体も、発泡スチロールの代替品として使われるケースが増えてきました。
生分解性プラスチックとは、微生物の一定の働きによって水と二酸化炭素(CO2)に分解される性質を持つ自然素材のプラスチックです。一般的な石油系素材のプラスチックと同様に使え、使用後は自然界に還るため環境負荷の軽減効果が期待できます。生分解性プラスチックは、発泡スチロールの代替品として家電の緩衝材や鮮魚輸送用の容器などに活用されています。
植物・動物由来素材の発泡体とは、名前の通り植物や動物由来の成分・素材を原料として発泡させたバイオマスプラスチックの一種です。生分解性プラスチックと同様に、使用後は自然界に還ります。具体的にはココナッツの殻やエビの殻を原料にした発泡体などが製品化されており、保冷バック・ボックスの緩衝材や輸送用の緩衝材として利用されています。
発泡スチロールの代替品を使うメリット
発泡スチロール代替品の使用には、環境保護やコスト削減、今後の法規制への対応といった多くのメリットがあります。
- 環境保護
- 発泡スチロールは海洋に漂流するとマイクロプラスチック化し、海洋生物に深刻な影響を与える可能性があります。発泡スチロールの代替品として使用される紙や生分解性プラスチックは自然由来の素材であり、廃棄物処理の手間や環境汚染のリスクを減らせます。
- コスト削減の可能性
- 代替品の中には、発泡スチロールよりも安価で手に入る素材もあります。たとえば、リサイクル紙や植物由来の素材は調達コストが比較的低く、経済的負担の軽減に大きく貢献します。発泡スチロールは適切に廃棄するために特別な処理が必要となるケースがある一方、代替品は処理が比較的容易であり、企業にとっては長期的なコスト削減につながります。
- 今後の法規制への対応
- 2022年には国内で「プラスチック資源循環促進法」が施行され、プラスチックの使用削減やリサイクルの強化がより求められるようになりました。こうした法規制の厳格化は、日本国内に限らず海外でも進んでいます。
発泡スチロールもプラスチック製品であるため、今後さらに規制が強化される可能性があります。そのため、早期に発泡スチロールを代替品へ切り替えることは、規制に対応した企業運営を可能とし、SDGsの取り組みへのアピールになるなど、ブランドイメージや競争力の向上にもつながります。
欧州のプラスチック規制はどうなっている? 最新状況を解説!発泡スチロールの代替品となるNISSHA製品

NISSHAでは、発泡スチロールの代替品となる「Pulp Series(パルプシリーズ)」を取り扱っております。Pulp Seriesは、パルプを主原料とした成形品です。プラスチックを使用していないため、石油資源の消費や環境汚染のリスクを抑えられます。
Pulp Seriesは、紙の風合いを残したまま、高いクッション性を持つことが特徴です。製品の形状に合わせて成形できるため、複雑な形状や複数の部品のある製品もしっかりと固定できます。そのため、トレーや外箱、梱包資材などに適しており、医薬品や化粧品、産業機器、日用品など、幅広い分野のパッケージングに活用されています。

発泡スチロールの代替品をお探しならNISSHAにお任せください
製品の容器や包装・梱包資材に発泡スチロールの代替品である紙や生分解性プラスチックなどのエコ素材を導入すれば、環境への負荷軽減や法規制への対応が可能となります。
NISSHAでは、サステナブルかつ高機能な製品を豊富に取り揃え、各企業様のニーズに最適な商品を提案しております。発泡スチロールをはじめとしたプラスチックに代わる梱包資材や包装資材をお探しの方は、ぜひNISSHAにご相談ください。




